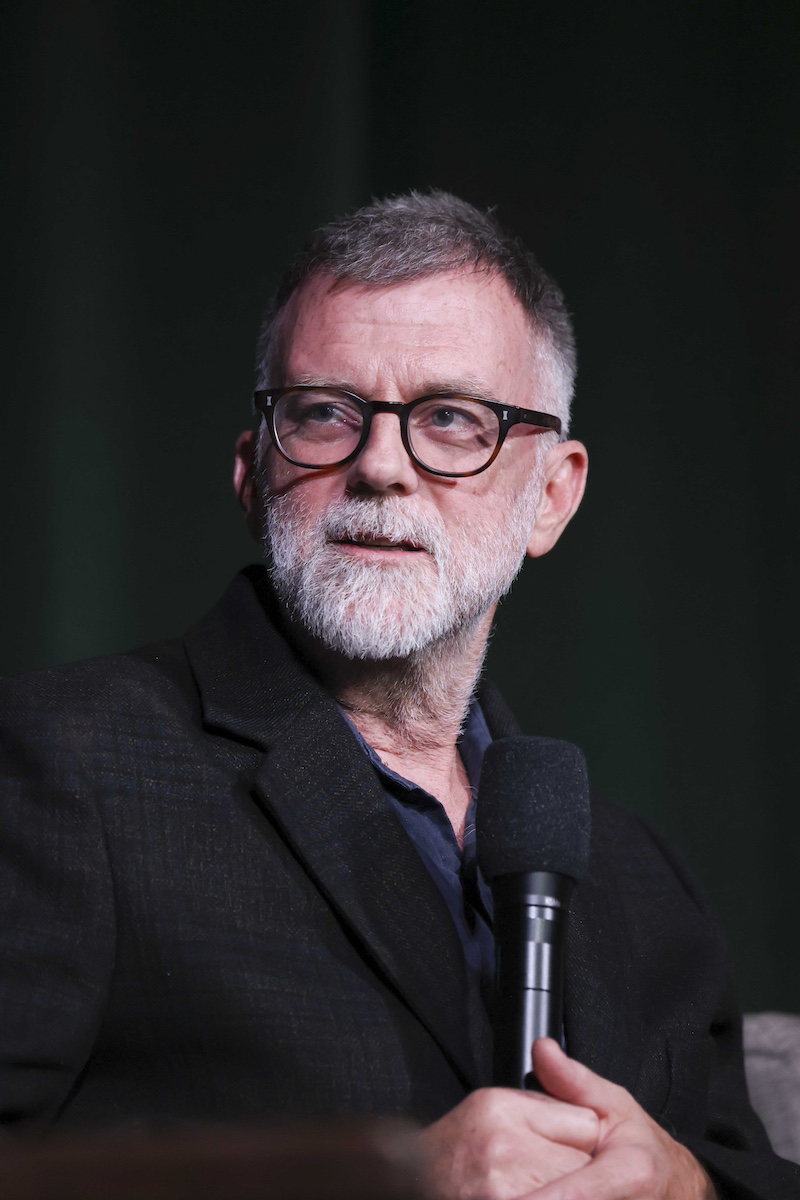世界三大映画祭(カンヌ、ベルリン、ヴェネツィア)の全てで監督賞を獲得した唯一の人物であり、現代映画界をけん引する監督、ポール・トーマス・アンダーソン(Paul Thomas Anderson)。「マグノリア」や「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」をはじめ、数々の傑作を世に送り出してきた名匠の待望の新作「ワン・バトル・アフター・アナザー」が10月3日、ついに公開された。娘の誘拐を機に再び争いへと身を投じる元革命家の男の奮闘を描く本作には、レオナルド・ディカプリオ、ショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロをはじめとする超豪華キャストが集結。破格のスケールと熱量で展開されるアンダーソン監督の新境地とも呼ぶべき本作は既に各方面から絶賛されており、米批評サイトRotten Tomatoesでは98%の高評価を獲得。「2025年最高の映画」との声も多数で、今年度の賞レースでも有力候補として期待がかかる一作である。
親子ドラマ、アクション、コメディー、社会派といったさまざまな側面を持つ本作をアンダーソン監督はどのようにつくり上げたのか。企画の立ち上がりから、念願となるレオナルド・ディカプリオとの共作、驚異的なカーチェイスシーン誕生秘話、偉大な映画監督たちとの個人的なつながりに至るまで、たっぷりと語ってもらった。
構想20年「ワン・バトル・アフター・アナザー」
——カップルの愛を描いた2本の映画「ファントム・スレッド」と「リコリス・ピザ」に続く本作では親子の関係に焦点を当てていますね。「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」でも扱った普遍的なテーマですが、家族や親子関係のどういう部分に共鳴したのでしょうか?
ポール・トーマス・アンダーソン(以下、アンダーソン):家族関係というものは、ドラマにとって常に優れた題材です。親と子、兄弟姉妹の間で起こることを描くだけでも成立する。そこに惹かれているのかもしれません。ドラマチックな可能性に満ちた、豊かな土壌であるところが大好きなんです。私は本作を書き始めた頃に父親になったので、自分の感情や経験を一番良い形で取り入れたいと考えていました。
——本作の題材には政治的な側面もつきものだったと思いますが、その点はどのように扱おうと考えたのでしょうか?
アンダーソン:先ほどの答えが今の質問の答えにもなっていると思います。言い換えるなら、私には政治を題材にした映画は書けない。面白くないからです。私が面白いと思うのは人と人との間に芽生える感情。政治は興味深い舞台や背景にはなるけれど、物語というものはどんな舞台設定に置き換えても成立しなければいけないものだとも考えています。宇宙でも、中世でも、どこが舞台だってそう。私にとっては、人間関係——家族や恋人、仕事相手など——の礎こそが物語を面白くする唯一の要素だと思っています。
——1980年代が舞台のトマス・ピンチョン著「ヴァインランド」から着想を得つつも舞台を現代に置き換えていますね。思えば監督が時代設定を現代にした長編作品は「パンチドランク・ラブ」以降23年ぶりかと思いますが、舞台を現代にした理由を教えてください。
アンダーソン:現代を舞台にした映画をつくることにとても刺激をもらえました。私は長いこと別の時代を舞台にした作品ばかりを手掛けてきたこともあり、現代が舞台の作品の方がつくるのが簡単で、かつ挑戦的であるように思ったんです。現代の物語であれば、外に出ていつでも好きなものを自由に撮影できるから簡単なんです。これまでの作品のように、時代を再現する制約に縛られるとそうはいきませんから。一方で現代劇が難しいのは、現代の技術やスマホといったものを、誰もが今まさに体験している通りに表現しなければいけないところです。逃げ場がない。それは良いことなんですけどね。
——革命家と娘の物語を、今日的な社会状況への風刺を込めつつ、魅力的なカーチェイスとともに描いていますね。構想20年と伺いましたが、複数ある要素のうち最初は何を主軸にして企画を進めていったのでしょうか?
アンダーソン:企画の出発点は何だったかな……。覚えているのは、映画の冒頭部分の大半が別の物語として考えていたということ。砂漠を舞台にした賞金稼ぎの話なんですが、内容や展開もぼんやりとしか覚えていません。そもそも物語と呼べるようなものでもなく、イメージの連なりといったものでした。でも砂漠でカーチェイスをするようなエネルギーに満ちた作品をつくりたいということは、漠然とした夢としてあったんです。それがこの物語の起点として覚えていることですね。その最初のアイデアは、本作の中で生き続けています。終盤に登場する賞金稼ぎのキャラクターの中にね。彼の仕事はもともと(革命家の)娘のウィラを誘拐し、殺すことだった。でも計画を変更し、彼女が他の人間に殺されるよう手配して、その場所へと連れていくことになる。それが砂漠を舞台にした追跡劇につながっていく。そうしてついに念願のカーチェイスを実現することができたんです。
——監督念願のアクションに加え、本作はヒューマンドラマやコメディー、スリラーといった複数のジャンルを自由に横断しています。そういった異なるジャンルのバランスをどのように考えて物語を構築していったのでしょうか?
アンダーソン:確かにジャンルのバランスは取れていると思いますし、そう見えるのも分かります。ただその点は特に意識してはつくっていません。一番に考えたのはプロットをどう掘り下げていくかということ。いろんな要素が満載のプロットでしたから。映画づくりにおいてプロットというのはときに軽いもののように考えられがちですが、本作においてはプロットと構造こそが全てでした。「ウィラはどこにいて、どうやってそこまで辿り着く?」「立ちはだかる勢力や壁はどんなもの?」というように、プロットに集中していったんです。アクション映画になったのもこのプロットだったからです。大抵のアクション映画はただ車がぶつかり合うだけで、良い演技や巧みな感情表現はあまり期待できません。ですが我々は皆、感情や情緒、登場人物の内面に対する思い入れが強く、単なるカーチェイス映画を作るつもりは毛頭ありませんでした。我々の人生においても、意味のあるものでなければならなかったんです。私にとっては父親になったこと、父親であることが自然に表れた作品になりました。
レオナルド・ディカプリオとの初タッグ
——主演を務めたレオナルド・ディカプリオと知り合ったのはいつ頃なのでしょうか?
アンダーソン:レオとは本当に長い付き合いで、もう25年以上になります。「ボーイズ・ライフ」(1993)で彼のことを初めて観て、完全に夢中になりました。私は彼の5歳年上なんですが、当時はその年の差がもっと大きく感じられたんです。私が25歳で、彼が19か20歳くらいの頃ですかね。ともかく、それまで観てきた中でもっとも刺激的な役者だと感じたんです。彼はみるみる頭角を現し、次々に素晴らしい演技を披露していきました。「ギルバート・グレイプ」(93)、「太陽と月に背いて」(95)、「バスケットボール・ダイアリーズ」(95)に「ロミオ&ジュリエット」(96)。名演に次ぐ名演ですよね。
そんな彼に初めて出会ったのは「バスケットボール・ダイアリーズ」の公開前。ジョン・ライリーが紹介してくれたんです。今では有名な話ですが、私は彼が「ブギーナイツ」(97)の主人公にぴったりだと考えてオファーしました。ですが、彼は「タイタニック」(97)が控えていて、その作品で要求されるであろうものの大きさに不安を感じていたんです。レオはそういった気持ちをきちんと話してくれただけでなく、親切なことにマーク(・ウォールバーグ)と話すように勧めてくれました。役者がオファーを辞退する際に別の俳優を推薦するなんて心が広くなければできないこと。レオはマークと「バスケットボール・ダイアリーズ」で共演したばかりで、マークのことを「本当に、本当に、本当にすばらしい役者だから」と言っていました。公開後に会った時は「タイタニック」の熱狂の真っ只中でした。それ以来の友人です。
——25年来の友人でありながらこれまでタッグを組んでいなかったディカプリオに、くたびれた革命家というキャラクターを委ねられると感じたのはなぜでしょうか?
アンダーソン:面白い質問ですね。だってレオにできない役なんてないでしょう? なんでもできる傑出した役者、それがレオなんです。とはいえ、特定の役者にぴったりハマる役というのはあります。演じる者の強みを最大限に発揮できるだけでなく、同時に挑戦する余地もあるような役ですね。皆さんご存知の通り、レオには観客を引き込み、笑わせることのできる素晴らしい才能があります。彼は幅広い感情を瞬時に表現できる。恐怖や混乱、怒りを表現しながら、それを痛ましくも滑稽にも感じさせることができるんです。そんな芸当ができる役者はそう多くありません。私は真に優れた俳優を何人も知っていますが、レオは観客を引き込む形でそういう演技をやってのける。
彼とは数年前にこんなことを話しました。「知り合って随分経っているし、年齢的に時間だってなくなってきている。だから今始めるべきだし、それが正しいことだ」と。そして実際に撮影初日を迎えた後、「我々のコラボはこれから何度も何度も繰り返さなければ」と感じました。この先、彼ともっと映画を作ることが本当に楽しみです。誰だってそう感じるとは思いますが(笑)。デヴィッド・マンの映画 にこんな台詞があります。「なぜ人は金を好むか? それは金だからだ」。レオに関してもそれと似たようなもの。「なぜレオナルド・ディカプリオが好きなのか? それは彼がレオナルド・ディカプリオだから」というように。人によってはそれをスター・パワーと呼ぶのかもしれない。興味深いですよね。
——主人公をディカプリオが演じることへの心強さは最初からあったと思いますが、撮影中に「この映画は素晴らしいものになる」と確信したのはいつでしょうか?
アンダーソン:撮影の3日目に「レオ演じる主人公がハイの状態で電話を取って、パスワードを一向に思い出せない」というシーンを撮ったんです。その時、カメラの横に座っていた私は、これから自分たちがつくり上げようとしている物語の可能性に胸が高鳴りました。映画撮影をしていると、その序盤にとてつもない自信と興奮をもたらしてくれる瞬間が時折あります。物語の導火線に火がつく瞬間と言いますか。それを3日目のその撮影で感じたんです。電話を受けて、ウィラを見つけられないと悟ったあの瞬間こそが、物語を推進する決定的な瞬間になりました。それはつまり撮影の早い段階でハードルが高く設定されてしまったということでもありますが。
映像へのこだわり
——本作は35ミリフィルムとビスタビジョンカメラで撮影されましたね。ビスタビジョンカメラに関しては「ザ・マスター」撮影時に誰かが持ってきたボロボロのカメラを、近年になり修理して本作で採用したと伺いました。最近では「ブルータリスト」があったくらいで、ビスタビジョンで撮影された作品は今やほとんどありません。フィルムが2倍になる、カメラが大型化するなど撮影面では困難が多かったかと思いますが、ビスタビジョンで撮影したことで映像面にどのような効果が生まれたと感じますか?
アンダーソン:ビスタビジョンでの撮影はすばらしかったですよ。映画に取りかかる際には、どのような感じの作品にしたいのかイメージを思い浮かべ、時にそのイメージが物語を形づくっていくこともあります。この作品に関して言えば、アイデアはかなり分散的でした。その一方で、ドキュメンタリーのように即興的で、美しくも洗練されてもいない方が物語的にも良いのではないかと考えたんです。序盤に関してはそれで上手くいったと思うんですが、舞台が砂漠に移ってからはよりドラマチックかつ壮大で、ワクワクするような何かも必要だと感じました。それらを同時に実現できるのがビスタビジョンカメラだったんです。説明するのが難しいんですが……フィルムで撮るとより立体的な感覚を映像に与えることができます。映像が映っている瞬間、キャラクターも物語も舞台も、まぎれもなく「そこに存在している」感覚と言いますか。この感覚を言葉にしようとすればするほどいつも支離滅裂になって、うまく説明できなくなってしまいますね。
でもそれは劇場で実際にその映像を観れば、体験として身体で感じられるもの。そのような感覚は言語化できなくていい。なんなら言語化できないものであるべきとすら思います。「感覚(feeling)」なんですから。ただその「感覚」が人々を興奮させるのか、それを味わえるような作品や劇場を探して足を運ぼうとするのか、それは私にはわかりません。……こうやって哲学を語っては人を退屈させてしまうのが私の癖なんです(笑)。
——アンダーソン監督初の本格アクションと聞いて期待していたのですが、予想を遥かに上回る映像に大興奮しました。とりわけ終盤のカーチェイスには圧倒されましたが、その斬新なシークエンスをどのように構築したのでしょうか?
アンダーソン:良い質問ですね。砂漠で物語が完結すること、ウィラにどんどん迫る人物がいること、カーチェイスがあることは撮影に取り掛かる前から分かっていました。ただそれがどのように劇的に重なって終わるのかは明確ではなかったんです。砂漠でのカーチェイスを撮るために、我々は何時間も車を走らせて、理想のロケーションを探しました。すると我々が「丘の川(river of hills)」と呼ぶ地域に差しかかったんです。その人影も何もない広大な空間を時速80~85マイル(約128〜137km)で走った時に、信じられないほどの緊張感が生まれたんです。というのも、その区画は走り切る最後の瞬間まで地平線の向こうが見えない。走り抜けた先の道路に何かあったら、悪いことが起きかねません。その丘陵地帯を走るうちに、「これはとても劇的で、映画的で、楽しいシーンになり得る」と気づいたんです。そこならウィラが状況を掌握する展開をつくることもできる。それはこの物語でもっとも面白い部分でもあります。ウィラが主導権を握って優位に立つ、そのイメージからどんどん物語の可能性が広がっていきました。「迫り来る敵と対峙したとき、彼女はどう行動するのか」「父親が現れたとき、どのようなことが起こるのか」というように。ネタバレになりかねないので、そこに関しては曖昧にしかお話できませんが(笑)。つまるところ、このシーンの絵コンテは用意していませんでした。まずロケ地を見つけ、撮影に必要なショットをリストとして書き出し、スマホを使い現地で何度も撮影しながら調整を重ね、試行錯誤を繰り返しながら完成させました。我々も特に誇りに感じているシークエンスなので、そこに言及してくれてうれしいです。
スピルバーグからの言葉
——スティーヴン・スピルバーグは本作について、「博士の異常な愛情」(64)を引き合いに出して絶賛していましたね。描かれる妄想や執着の程度やコメディーの性質は確かに共通すると思うのですが、彼の言葉をどのように受け止めましたか?
アンダーソン:「『博士の異常な愛情』のようだ」と言われるのは怖かったです。多くの映画監督たちが「博士の異常な愛情」のような作品を作ろうとして失敗してきたから。むしろ手を出すべきでない作品だと感じています。我々は「博士の異常な愛情」が自分たちと別次元に存在する作品であることを尊重すべきであり、模倣したり、いじったりすべき作品ではない。手を出してはいけない傑作なんです。もちろんスティーヴンにそう言われることは光栄なこと。褒め言葉として受け止めていますし、そう感じてもらえたことは尊重しますが、私が「博士の異常な愛情」をある種、触れてはいけない領域として感じているのは確かです。
——また映画史を定義してきた偉大な映画監督たちとの関わりについても教えてください。あなたはロバート・アルトマン監督の遺作である「今宵、フィッツジェラルド劇場で」(06)の撮影にスタンバイディレクターとして同行していましたよね。
アンダーソン:幸運なことに、私の人生はたくさんの映画や映画監督とのつながりによって成り立っています。その中でもロバート・アルトマンとの関係は、この上なく特別なもの。独自の言語を創り出した先人であり、私もとても深い影響を受けています。それどころか、彼の映画こそが私の映画製作を形作ってくれています。私は彼との関係の中で、一人の人間としての彼を知り、映画に反映された彼の人間性と映画の外側にある彼の人間性、その両方に触れることができました。それは私にとってなにより名誉なことです。また敬愛する多くの映画監督たちとも、そうした関係を築くことができました。ロバート・ダウニー、ジョナサン・デミ、マーティン・ブレスト、そしてもちろんスティーヴンもそう。映画監督として先を行く先輩方と出会い、その寛大な人柄を知ることのできる恵まれた立場にただただ感謝しています。ウィリアム・フリードキンとも知り合ったのですが、彼の優しさと寛大さに触れられたことはとても素晴らしい体験でした。
皆さんがそれを感じ取るかは分かりませんが、映画監督たちのあいだには信じられないほどの寛大さがあるんです。おそらくは寛大さ(generosity)という言葉が一番的確でしょう。分かちあい、守りあう、とても素敵な関係です。残念なことに私が敬愛する監督の中には、世代が異なるためにお会いできなかった方々がたくさんいます。そういった方々ともぜひ知り合ってみたかったのですが。少しとりとめもない話になってしまいましたね。
——映画監督して、あなたはそんな先人の名監督たちにどんな「借り」があると思っていますか?
アンダーソン:全てですね。全て、彼らのおかげです。
◾️映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」
◾️映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」
10月3日全国公開 IMAX®/Dolby Cinema®同時公開
出演:レオナルド・ディカプリオ、ショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロ、レジーナ・ホール、テヤナ・テイラー、チェイス・インフィニティ
監督/脚本:ポール・トーマス・アンダーソン
撮影:マイケル・バウマン、ポール・トーマス・アンダーソン
衣装:コリーン・アトウッド
音楽:ジョニー・グリーンウッド
2025年 アメリカ映画/2025年 日本公開作品/原題:ONE BATTLE AFTER ANOTHER
上映時間:162分/ビスタサイズ/2D/IMAX®2D/ドルビーシネマ2D/リニアPCM5.1ch+7.1ch+ドルビーアトモス(一部劇場にて)
配給:ワーナー・ブラザース映画
© 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
Dolby Cinema® is a registered trademark of Dolby Laboratories
https://wwws.warnerbros.co.jp/onebattlemovie/