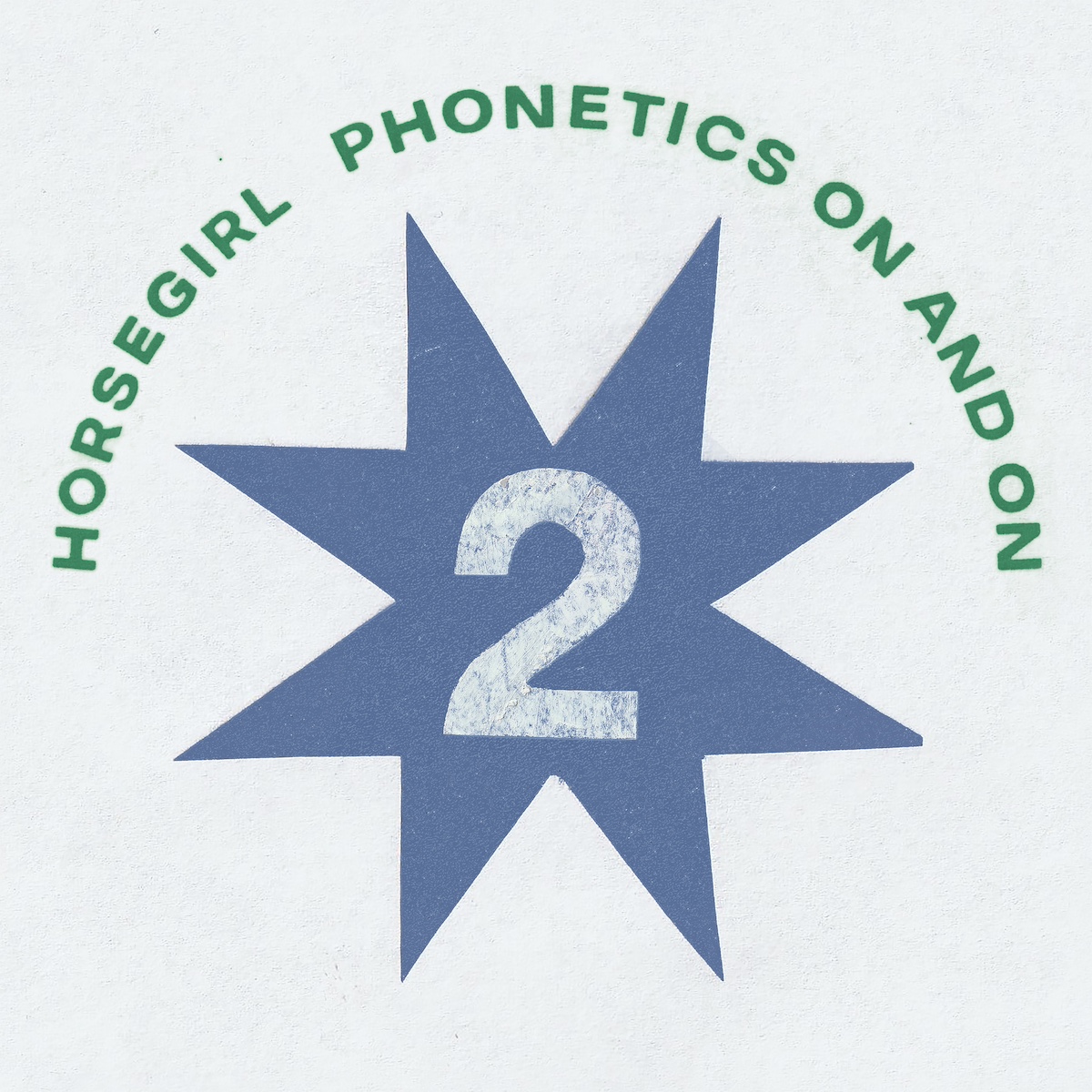2019年にノラ・チェン(g/vo)、ペネロペ・ローウェンスタイン(g/vo)、ジジ・リース(ds)が10代の時に始めたロック・バンド、ホースガール(Horsegirl)。地元シカゴのDIYなアート・コミュニティーから登場した彼女たちは、22年のデビュー・アルバム「Versions of Modern Performance」で一躍注目を浴び、アメリカのインディー・ロックを担う新たな世代として大きな期待を集めるようになった。そしてその後、メンバーの進学をきっかけに拠点をニューヨークに移し、今年2月にリリースされた最新アルバム「Phonetics On and On」は、全員が20代を迎え、新たな環境のなかで彼女たちに訪れた変化を象徴するような作品だった。3人がインスピレーションを受けてきた、1980年代や90年代のインディー・ミュージックへの愛とリスペクト。加えて、新たなプロデューサーにケイト・ル・ボン(ウィルコ、デヴェンドラ・バンハート)を迎え、そこに多彩な音色をもたらした奥行きのある楽器構成と、“余白”を活かしたミニマルでコントラストの効いたプロダクション。さらに、内省的なムードを増した繊細な心象風景の描写が、絆を新たにした3人の距離感やフレンドシップをみずみずしく浮かび上がらせている。「Phonetics On and On」には、そんな大人になる手前の、またミュージシャンとしても大きく揺れ動いている彼女たちの姿が鮮やかに刻まれている。
去る9月中旬、初めてのジャパン・ツアーを行ったホースガール。今回インタビューに応えてくれたジジは、最年長のメンバーで、他の2人とは異なり大学には通わず、友人とZINEを発行するなど音楽と並行して独自の活動を楽しんでいる。リード・ボーカルをとることはないジジだが、けれどジジには伝えたいことがあり、表現したいアートがある。「この新しい感覚を持って次にどんな音楽をつくれるのか、その可能性にワクワクしてる」。新作「Phonetics On and On」をへて、そう手応えと期待を口にするジジに、アルバムの制作背景、そして自身/3人の今とこれからについて聞いた。
ブラック・ミディやBCNRへの共感
——昨夜はジャパン・ツアーの初日で、日本での初めてのライブになりましたが、いかがでしたか。
ジジ・リース(以下、ジジ):本当に素晴らしいライブでした。日本のお客さんはすごく静かだと聞いていたんですけど、実際には全然そんなことなくて。もちろん、とても礼儀正しくて、ステージの準備をしている間はしんと静まり返っていて――アメリカではみんなその時間におしゃべりしているから(笑)、あの静けさは新鮮でした。演奏が始まると、真剣に耳を傾けてくれているのが伝わってきて、本当に音楽を“聴きに来てくれている”という感じがしました。曲もよく知ってくれていて、特定のフレーズや盛り上がる瞬間で「ウォー!」と歓声が上がるのもうれしかった。あの反応は、曲を深く理解して楽しんでくれている証拠なんだと思います。
——新作の「Phonetics On and On」では、無駄な要素を削ぎ落として、ミニマリズムや“空間”という概念で実験してみたかったと話していました。そうした”余白”があるぶん、ライブではアレンジの自由度も高いのかなと。
ジジ:うん、その“間(ま)”や“余白”を楽しめるようになったと思います。最初は、音の間にあまりにも空間がある曲を演奏するのが正直ちょっと怖かったんです。観客席の静けさや会場の広さの中で、自分たちの音だけが響いているような感覚があって。でも今では、その静けさこそが大きな力になっている。10代の頃は、お客さんが体を動かしているかとか、会場の熱量ばかりを気にしていたけれど、今は自分たちの音で“空間そのもの”をコントロールできている実感があります。スタジオでミニマルに仕上げた曲に、どうエネルギーをのせて、どう観客に伝えるかを考えてアレンジを調整する作業はとても楽しい。それに、シンプルでミニマルなアレンジにすると、聴いている人が一音一音に集中してくれているのが伝わってくるんです。
——アルバムの話を続けたいところですが——そんなTシャツ(胸に「I ❤️ Black Midi」のロゴ)を見せられたら、触れないわけにはいかないですね(笑)。
ジジ:(笑)。実はペネロペとノラと私が10代の頃、ちょうどブラック・ミディが活動を始めて、デビュー・アルバムを出した時期で、彼らに夢中になったんです。少し年上なだけなのに、ギターを使ってあんなに狂った実験的な音楽をやっているのを見て、ものすごく刺激を受けて。当時の彼らのライブは、自信のなさというか、若さゆえのぎこちなさがあって――観客に一言も話しかけず、ほとんど目も合わせずにひたすら演奏し続けるようなスタイルで、それがまた自分たちには共感できたんです。音楽的には自分たちと全然似ていないけれど、地球の別の場所から現れた「同じ音楽オタク仲間」のように感じられて(笑)、精神的にはすごく近いところにいると思えたんです。それが当時の自分たちにとって大きな励みになりました。
このTシャツは確かノラと一緒に(ライブ会場で)もらったんじゃないかな。夏の間ずっと着ていて。日付がプリントされていて、自分でちょっとカットオフしたんですけど(笑)。確かニューヨークの公演で手に入れたはずで、もしかしたらそのデザインはニューヨーク限定だったのかもしれない。ブラック・ミディは、自分がこれまでで一番多くライブを観たバンドの一つだと思う。常にツアーをしていたし、自分たちのサウンドエンジニアが彼らのツアーに帯同していたこともあって、自然とつながりがあって。だから今でも、彼らのことを思い出しては、このシャツを着たくなるんです(笑)。
——そのブラック・ミディへの共感というのは、彼らやブラック・カントリー・ニュー・ロードなども含めた、サウス・ロンドンの「The Windmill(ウインドミル)」(※ブリクストンにあるキャパ150人程度の小さなヴェニュー/パブ)周りのバンド・シーンへの共感にもつながっていたのでしょうか。
ジジ:間違いなくそうだと思う。自分たちが10代の頃、ロンドンでああいうシーンが起きているのを知るのは、本当にワクワクすることでした。当時のシカゴにはまだ“自分たちのシーン”と呼べるものがなかったし、せいぜい友だち数人がライブをやっているくらいで、バンド同士で共演する機会もほとんどなかった。そこにコロナ禍がやってきて、活動がさらに分断されてしまった感覚がありました。
だから「The Windmill」を中心としたあのシーンは、自分たちより少し年上の世代で、“これこそが目指す理想だよね”と指させるような存在でした。この夏、初めて実際に「The Windmill」に行ってみたんだけど、びっくりするほど普通のバーで(笑)。でもそういうものですよね。頭の中でロマンチックに思い描いていて、いざ行ってみると「あ、ただのパブだ」っていう。でも若い頃は、そうした場所や空気がものすごく大きな影響を与えてくれたんです。
そして今では、ブラック・カントリー・ニュー・ロードやブラック・ミディのメンバーと同じステージに立つこともあって、自然に交流が生まれています。フェスの話を気軽にできる仲間なんて、日常生活ではなかなかいないので、そういう関係は本当に貴重だなって。最近もブラック・カントリーのルイスに「日本でライブしたことある?」ってメッセージを送ったら、「全部食べ尽くして、全部飲み尽くせ」って返ってきて(笑)。最高のアドバイスですよね。
2ndアルバムとニューヨーク生活
——ところで「Phonetics On and On」の制作では、ミニマリズムと並行して、ポップ・ミュージックのソングライティングや構成も意識したと話していました。具体的に参照したポップ・ミュージックはありましたか。
ジジ:自分たちにとって「ポップ・ミュージック」というのは、あくまで“カッコ付き”なんです。実際はかなりロック的な側面が強いというか。例えば、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Loaded」のように、ヴァース、コーラス、ヴァース、コーラス、ブリッジ……といったクラシックなポップ・ソングの構成。そういうフォーマットで曲を書くことが、今ではすごく魅力的に感じられるんです。
1stアルバムの頃は、曲の形式そのものが実験的なものに惹かれていました。でも経験を重ねて、“自分たちなりのポップ・ソング”をつくってみたいという気持ちが強くなってきたんです。だからもちろん、自分たちのつくるものは純粋なポップ・アーティストのようにはならないし、オリヴィア・ロドリゴのような音楽でもなくて。でも、その“自分たちなりのポップ”を探る試み自体が面白い。自分が今好きなアーティストたちもそれぞれの形で“自分のポップ”を追求していて、その結果として生まれる音楽がすごくユニークで刺激的なんです。
——そうした曲づくりの変化には、ニューヨークに移り住んだことも影響としてあると思いますか。
ジジ:うん、ニューヨークでの生活が、私たちの音楽の変化に大きな影響を与えたのは間違いないと思う。
最初の1〜2年は、ただ圧倒されるばかりでした。どこに行っても人がいて、匿名のまま人の流れに溶け込んでしまいそうな感じがして。でも、ここ1年半くらいでようやく“この街に根を下ろした”という感覚が持てるようになってきました。ペネロペとノラと一緒に住み始めてからは、ちゃんと自分たちの拠点ができたという安心感もあって。今では心から“ここが自分の居場所だ”と思えるようになりました。
ニューヨークでは常に何かが起こっていて、それが時にはしんどく感じられることもあるけど、同時に“世界の中心にいる”ような高揚感を与えてくれる。だから、暮らしているだけでインスピレーションを受ける場所なんです。
——ニューヨークでは新たな音楽との出会いはありましたか。
ジジ:私たちがニューヨークに引っ越して、ペネロペとノラはそこで大学に通い始めたんですけど、その頃に出会ったのは、ちょうどバンドを始めたばかりの同世代の人たちで。みんなローカルなDIYショーに夢中になっていて、その姿にとても刺激を受けました。だから、今でも友達のほとんどはバンド仲間なんです。シカゴにいた頃もそうだったし、ニューヨークに来てもそれは変わらない。自分たちの周りには常に音楽をやっている仲間がいて、そのコミュニティのなかで日々生きているような感覚があります。
それに、ニューヨークって本当に“あらゆるバンドが必ずやってくる街”なんです。シカゴもそうだったけど、規模はもっと大きい。例えばヨ・ラ・テンゴなんて、ニューヨークに住んでいると何度もライブを見ることができる。彼らはいつもどこかで演奏しているんです(笑)。そんなふうに音楽が日常のすぐ隣にあるというのも、この街ならではの魅力だと思う。
最近は、ゴッドキャスター(Godcaster)というニューヨークのバンドと一緒にツアーをしました。もう8年くらい活動していて、私たちより少し年上だけど、本当に素晴らしいバンドです。それから、まだ正式に作品をリリースしていない友達のバンドもたくさんいて――ガイスクレイパーズ(Guyscrapers)、デブリス・バードット(Debris Bardot)、アウトバーン(Autobahn)とか。まだほとんど知られていないと思うけど、ローカルのライブではどのバンドも本当に面白いことをやっています。
——ちなみに、〈Matador(マタドール)〉のレーベル・メイトであるウォーター・フロム・ユア・アイズもニューヨークのグループですよね。
ジジ:あ、そうそう!彼らとはいろんな場面で顔を合わせることが多くて。彼らは毎年、ボートの上でライブをするんですけど、今年はノラと一緒に観に行きました。あの独特の雰囲気は最高だった。それから、ファンタジー・オブ・ア・ブロークン・ハート(Fantasy of a Broken Heart)という、ウォーター・フロム・ユア・アイズのツアー・メンバーが別でやっているプロジェクトも素晴らしくて。実は「The Windmill」でライブを観たことがあるんですけど、彼らも同じシーンの中で自然につながっていった仲間たちです。
——シカゴであなたたちが運営していた「Hallogallo(ハロガロ)」のように、ニューヨークでも共感を寄せることができるコミュニティーやシーンを見つけることはできましたか。
ジジ:そうですね……そこは私たち自身も少し年齢を重ねたことで、“シーン”というものとの関わり方が変わってきた部分もあると思います。10代の頃はまだ子どもだったので、ライブハウスを借りることも入ることも難しくて、自然と仲間同士で支え合うような雰囲気がありました。だからこそ、みんなで協力して何かをやらなきゃいけない、という感覚が強かった。でも今は、ニューヨークで自分たちなりのコミュニティーを見つけつつ、より自由に活動できるようになりました。自分たちでショーを企画することもできるし、好きなライブにも行ける。バーにも普通に行けるし(笑)、みんなお酒を飲める年齢になったので、ショーによってはパーティー的な雰囲気になることもある。10代の頃は「音楽をやる」ことだけが全てだったけれど、20代になってからは「楽しむ」というムードも加わってきた気がします。特にニューヨークは、そうした空気を自然に後押ししてくれる街だと思います。
ただ、私たちはそういう“飲んで騒ぐノリ”にどっぷり浸かっているわけではなくて。酔った状態で演奏するのは苦手だし、むしろ緊張してしまう(笑)。だから、ニューヨークで新しいコミュニティーを見つけた今も、それがどう変化していくかは、自分たちの年齢や環境とともに少しずつ形を変えていくんじゃないかと思っています。
ジジがつくるZINE「My Boyfriend」
——去年来日したフリコ(Friko)のメンバーに話を聞いた時、シカゴのDIYシーンの特徴は、音楽とビジュアル・アートが密接に結びついているところにあると教えてくれました。ニューヨークにも、そういう側面が強くあるような印象があります。
ジジ:そうですね。自分がニューヨークで出会った人たちも、必ずしも音楽だけをやっているわけではなくて。友人たちは皆それぞれの分野で表現をしていて、常にアーティストたちに囲まれているような感覚がある。そういう環境の中で過ごしていることはとても刺激的です。それに、若い頃は何もかも音楽中心だったけれど、今は私たち自身も音楽以外のアートの中に自分を見出すようになっていて、それがすごく充実感を与えてくれています。周りには、自分たちとは違う方法で表現しているけれど、同じくらい真剣に取り組んでいる人たちがいて、その距離感がとても近い。ファッションとは少し距離があるかもしれないけれど、美術や写真、映像制作といった分野は音楽と強く結びついていると感じるし、そうした創作の交差点に身を置いていることが刺激になっているんです。
——その“音楽以外のアート”の話で、ジジさんが今つくっている「My Boyfriend」というZINEについて教えてもらえますか。
ジジ:これまでに3号つくっていて、今は4号目を準備しているところです。「My Boyfriend」というタイトルには、女性がしばしば男性に“教えてもらう”とか“代弁してもらう”という構造に依存してきたことを、ちょっとひっくり返して遊びたいという気持ちが込められていて。「彼氏が全部知ってる」「彼氏が正しい」みたいな決まり文句を借りながら、実際には自分の声を重ねていく。つまり、“これは私が言ってるんじゃない、私のボーイフレンドが言ってるの”っていう体(てい)で発言するんです。それがちょっとバカバカしくて、でも同時にユーモアと力強さがある。そういう“stupid art(バカげたアート)”が大好きなんです。
しかも、このZINEは自分ひとりの制作ではなくて、コミュニティーをベースにした活動でもある。友人たちに“この声のトーンに合う作品をつくってほしい”とお願いして、一緒にZINEをつくる。だから“ボーイフレンド”は特定の誰かではなくて、ニューヨークやシカゴで関わってきた仲間たちの集合体のような存在なんです。とにかく、周囲の人たちと一緒に何かをつくりたいという気持ちが強くて、それがこのZINEを始めた理由でもあって。今や誰もが自分のZINEを持っている時代だから。
——シカゴにいた時もZINEとホースガールはとても近い関係にありましたが、改めてジジさんにとって「ZINE」はどんな存在だと言えますか。
ジジ:今の時代って、なんでもオンラインで手に入るし、情報も音楽も、指先一つで届く。それはもちろん便利なんですけど、だからこそ、CDやレコード、本、ZINEのようなフィジカルなメディアを持つことが、今はすごく大事だと思うんです。
例えばライブのフライヤーを刷って手渡すとか、そういう行為もとても素敵だと思う。スマホで撮った写真って、気づいたらどこに保存されているのか分からなくなってしまうけれど、本棚に積まれたZINEの束は、人生の記録としてずっと残っていく。どこにいたか、誰と出会ったか、何をしていたか、そうした痕跡が物理的なアーカイブとして残るんです。しかもZINEってすごくカジュアルな媒体で、自分ひとりでつくることもできれば、ちゃんと製本して“作品”のように仕上げることもできる。その“雑さ”をあえて楽しめるのも魅力で、だからこそ人のユニークな声が、より生々しく表現されるんだと思います。
——ジジさんの中で、ZINEをつくることと音楽、ホースガールとしての活動はどう結びついていますか。
ジジ:私たちはすごく若い頃に(レコード会社と)契約して活動を始めたので、“自分の声”を見つけるのが難しいと感じる時期もありました。もちろん、ペネロペやノラとのコラボレーションの中での“声”は自分自身の一部であり、ホースガールというバンドとして一つになっている感覚は揺るがない。でも同時に、3人それぞれが“自分自身の表現”を持つこともとても大切だと思うんです。
ホースガールでの関係性は、誰とでも築けるものではないし、本当にかけがえのないもの。だけど、そこで学んだ“声を混ぜ合わせる喜び”とか“コラボレーションの精神”は、自分のZINEづくりにも強く反映されているんです。もしホースガールがなかったら、誰かと作品を共有する楽しさや、一緒につくり上げることの意味を、ここまで深く理解できなかったと思う。
ニューヨークに来てからは、自分ひとりで作品をつくることにも挑戦したくて、絵を描いたりペイントしたりもしています。そうやって一人で何かをつくることが、逆にペネロペやノラと音楽をつくる時の信頼や充実感を、さらに強くしてくれる。結局は全部がつながっていて、どれも同じように自分を満たしてくれる表現なんだと思います。
2ndアルバムで得た成長と自信
——ところで、ここ(取材場所)に来る前にレコード・ショップに立ち寄られたそうですね。最近よく聴いているレコードや、魅力を再発見した音楽とかありますか。
ジジ:最近はデヴィッド・ボウイをよく聴いていて。特に「Hunky Dory」。誰もが知る名盤だから、“新しい発見”というよりは、改めて光を当てたいという気持ちで聴き返している感じかな。T・レックスの「Electric Warrior」もお気に入りで、ここ最近はちょっとした“グラム・ロック期”にいる感じなんです(笑)。
——それって何かきっかけがあったんですか。
ジジ:子どもの頃、クイーンにすごくハマっていたんです。その後、ペネロペやノラと出会った時にT・レックスを聴くようになって、そこから自然と、自分たちが最初のアルバムをつくっていた頃に聴いていたような音楽につながっていった気がします。
だから今、改めてT・レックスやデヴィッド・ボウイを聴き返しているのは、子どもの頃の“好き”を、大人の視点で再発見しているような感覚なんです。昔はただ“この曲がかっこいい”としか言えなかったけれど、今はアレンジや歌詞、構成にまで耳がいく。ボウイやT・レックスの歌詞って本当に特別で、しかも音楽そのものと完璧に結びついているように感じる。ボウイという存在自体が革命的だし、キャリアの築き方、生き方そのものに強い刺激を受けています。自分たちも歳を重ね、バンドとしてのキャリアを積み上げていくなかで、彼から学べることは本当に多いと感じます。
——ちなみに、先ほど新作の参考になった作品の話でヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Loaded」を挙げていましたが、ザ・フィーリーズの「The Good Earth」も曲づくりの大きなインスピレーションになったと聞きました。「人生が一変した」と話していましたが。
ジジ:はい(笑)。私たちって、ペネロペとノラと出会った頃からずっとフィーリーズのファンだったんです。でも知っていたのは(1stアルバムの)「Crazy Rhythms」だけで。あのアルバムの曲は素晴らしいんだけど、やたら長いインスト・ブレイクがあったりして、すごく実験的なんです。で、「The Good Earth」を聴いた時、その実験的な感覚はありつつも、すごくクラシックなポップ・ソングの構造があって、しかもギターの鳴らし方とか、音の選び方に妙に奇妙さが潜んでいて。完全に虜になりました。
そのアルバムを初めて聴いたのはツアーの車の中で、サウンドエンジニアのジェシーが流してくれたんです。それで、3人とも一瞬で「これだ!」ってなって。ちょうど自分たちの新しいアルバムを書いていて、ケイト・ル・ボンと一緒につくる準備をしていた頃だったから、あの出会いは大きな転換点でした。それ以来、スタジオでもフィーリーズはずっと参照点になっていたし。
フィーリーズってヴェルヴェット・アンダーグラウンドを愛していたバンドでもあって。私たち自身もヴェルヴェッツが大好きで、そうやって“ヴェルヴェッツを愛するバンド”をまた愛するという関係が、時代を越えて受け継がれていく感じがある。そうしたつながりのなかで、自分たちなりの音楽を作っているんだという感覚を、改めて強く意識させてくれたんです。
——あのアルバムって、R.E.M.のピーター・バックが共同プロデューサーとして関わっているんですよね。
ジジ:え、そうなんですか? 全然知らなかった。正直、R.E.M.って有名な曲しか聴いたことがなくて……もちろんどれも素晴らしい曲だけど、「The Good Earth」に関わっていたなんて。それを知ったら、もう一度聴き返した時に全然違う角度から受け止められそう。
——仮にホースガールの次のレコードを想像するとしたら、今回のミニマリズムや“ポップ・ミュージック”の曲づくりさらに掘り下げた先に、例えばR.E.M.の「Automatic for the People」のようなアコースティック・サウンドをモダンなプロダクションで表現する方向もあれば、あるいはケイト・ル・ボンとの共同作業の延長として、ステレオラブみたいな多彩な器楽構成と音響構築を融合させる方向性も考えられると思うんです。ジジさんの中では、現時点でどちらの感触が近いですか。
ジジ:そうだな……たぶん、その“中間”にいるような気がします。どちらの感覚もよくわかるし、それにさっきの話を聞いて、改めてR.E.M.のアルバムを聴き返してみたくなっているところで。それに、ペネロペは多くの曲をアコースティック・ギターで書くんです。「Julie」も最初はアコギでつくられた曲で。去年ブリーダーズと一緒にツアーをした時、キム・ディールがアコースティックを弾いていて、そのスタイルが本当に素晴らしかった。ロック・ソングの中でアコースティックを使うのってすごく面白いし、私たちも今後のライブや制作に取り入れていきたいと思っています。
ただ、私たちは曲をつくる時に“こういう最終形にしよう”と最初から決めるタイプではなくて、自然に生まれてくる流れに導かれながらつくっていくんです。今回のアルバムでは“もっとミニマルにしたい”という意識はあったけれど、全体像が見えてきたのは曲が揃ってからで、スタジオに入って初めて“これだ”と確信できた感じでした。
頭の中で完璧な理想を描くよりも、制作の過程で音が変化していくことを大切にしていて、そこにこそ創造の面白さがあると思うんです。だから次の作品についても、構想はありつつ、最終的にどう形になるかはまだ分からない。ある意味“宇宙に委ねる”感覚というか……だからこそ、また新しい曲を書くのが楽しみなんです。
——前作「Versions of Modern Performance」は、3人が大人へと向かう過渡期に制作された作品でした。人生の中でも特に多感で、変化を受けやすい時期の記録だったと思います。対して、今度の新作は3人にとってどんな作品になったという実感がありますか。
ジジ:1stアルバムは、まさに私たちがティーンエイジャーとして成長していく姿をそのまま刻んだ作品でした。2ndアルバムも“成長の物語”であることは変わらないけど、今回はそこに“自信”が加わったような気がします。
ミニマルなアプローチを選んだのも、その自信があったからこそだと思う。音で空間を全て埋め尽くすのは簡単だけれど、あえて“余白”を残すには確信と勇気が必要で。1stの頃からそうしたい気持ちはあったけれど、今回ようやく自分たちの声、そして互いのコラボレーションを信じられるようになった。だからこの作品を形にできたんだと思う。そして、その曲たちをライブで演奏していく中で、その自信はさらに確かなものになりました。今は、この新しい感覚を持って次にどんな音楽をつくれるのか、その可能性にワクワクしています。
PHOTOS:MICHI NAKANO
2ndアルバム「Phonetics On and On」
◾️Horsegirl 2ndアルバム「Phonetics On and On」
トラックリスト
01. Where’d You Go?
02. Rock City
03. In Twos
04. 2468
05. Well I Know You’re Shy
06. Julie
07. Switch Over
08. Information Content
09. Frontrunner
10. Sport Meets Sound
11. I Can’t Stand To See You
12. Ramona Song(Bonus Track for Japan)
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14538