PROFILE: 神谷将太/三越伊勢丹ホールディングスサステナビリティ推進部マネージャー
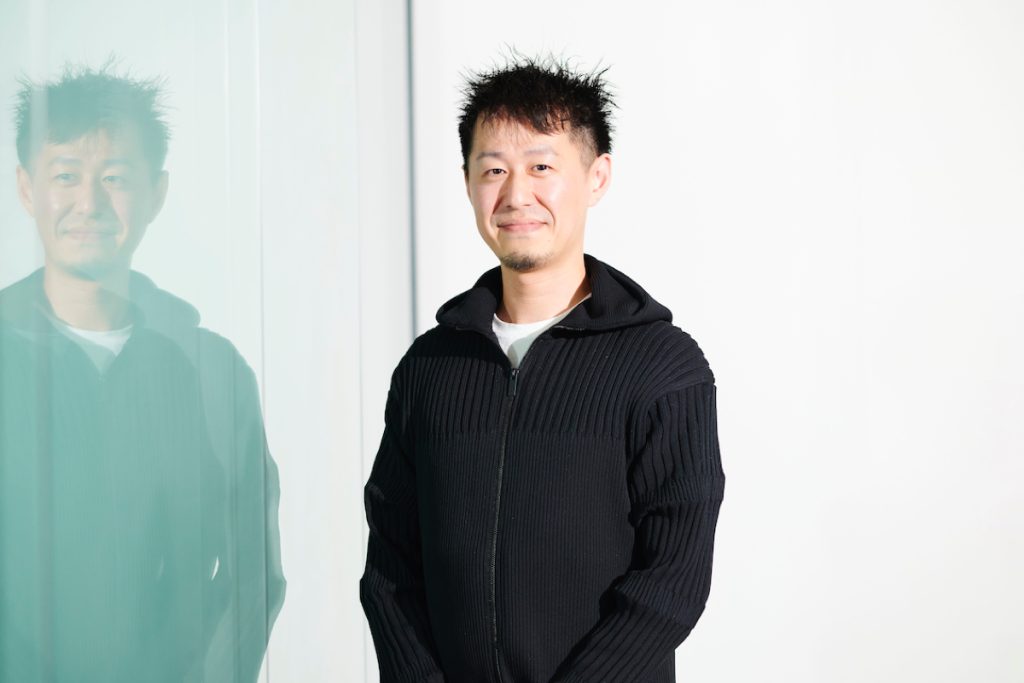
伊勢丹新宿店でリ・スタイル担当などファッションのど真ん中でキャリアを積んできた名物バイヤーがこのほど、三越伊勢丹ホールディングスのサステナビリティの要職に着任した。廃棄デニムを再利用して話題になった「デニム de ミライ」企画など、バイヤー時代の型破りな仕事を経て新しい部署で何を担うのか。神谷将太三越伊勢丹ホールディングス総務統括部サステナビリティ推進部マネージャーに話を聞いた。
サステナビリティ推進部の「営業」を担う
WWD:辞令をどう受け止めましたか?
神谷将太三越伊勢丹ホールディングス総務統括部サステナビリティ推進部マネージャー(以下、神谷):サステナビリティ推進部は2022年にできた部署です。改めてそのミッションを聞くうちに“やるぞ”とモチベーションが上がりました。経営に近い立場でサステナビリティのさまざまなことに関わり、知識や人脈を広げ、 また営業の現場に戻って活躍する。そういう循環も社は考えているようです。現場感覚と経験、社内外のつながりを生かして具体的な取り組みを推進したい。
WWD:具体的な業務を教えてください。
神谷:サステナビティ推進部が大きく3つのチーム、「環境」「営業」「エンゲージメント」に分かれており、私は「営業」チームでマネージャーを務めます。
WWD:営業チームの役割とは。
神谷: “シンク グッド(think good)”のプロジェクトを、百貨店グループのみならず関連各社全体で推進をしていくことと、サプライチェーンマネジメントです。百貨店事業としてスタートした“シンク グッド”は、今年度からグループ会社、関連事業を含めて推進します。グループ会社はホームページに載せているだけで37あり、不動産、金融などさまざまなチームがある。本当にいろいろな事業があるので、まずは弊社のことも改めて勉強したい。彼らと伴走して、時におお取り組み先をつなぎ“シンク グッド”を広げていく。サステナビリティの考え方に基づく戦略を勢いをもって構築したい。
WWD:サプライチェーンマネジメント業務を具体的に。
神谷:主にお取り組み先との対話です。最近は特にラグジュアリーブランドは自社の行動規範を持ち、こちらに提示されることも多い。昨年から、新宿店の商品チームを中心に現場のバイヤーが約500社のお取り組み先と対面で品質管理や法令順守、人権への配慮など双方の規範の話をしています。
WWD:1社ずつ話すのは労力ですね。行動規範を配って終わり、ではない、と。
神谷:対話を通じてお取り組み先がサプライチェーンの川上をどこまでさかのぼり、何を大切にしているかを把握できることは意味がある。小売りの立場だと川上の現実はなかなか見えないから、対話を通じてかなり勉強になっています。サステナビリティ推進部はグローバルの動きやリスクなどの情報共有をします。昨年までは学ぶ立場だったのですが今年は伝える側ですね。一方通行ではなく、現場が活かせる情報として伝えていきたい。
WWD:サステナビリティに携わると従来のファッションビジネスにはない言葉や価値観と出会うことが多いのでは?
神谷:勉強しなければ、はすごく実感しています。知らない用語、取り巻く法律もそうだし社内の行動規範や調達方針もそう。すでに明文化されたものはあるしバイヤーですからある程度は知っていたけれど、自分の言葉で言語化して人に伝えることはまた別です。
WWD:この職務で自身のどんな姿を目指していますか。
神谷:現場感覚と経験、あと社内外のつながりを生かして、具体的な取り組みを推進したい。
サステナビリティはカウンターカルチャーという意識だった

WWD:「営業」と聞くと何かを売るイメージですが、ここで言う「営業」は営業施策の横展開、という意味ですね。つなぎ、巻き込んでいく、それは神谷さんがバイヤーとして「デニム de ミライ」などで実践してきたことです。
神谷:そうですね、思い返せば、バイヤー着任2年目の2016年に工場の余剰生地をデザイナーとピックアップして多品種少量生産の提案をしたり、リ・スタイル プラス担当のときは、希少性×エシカルという設定で、「ファセッタズム(FACETASM)」や「コシェ(KOCHE)」などと環境配慮素材や余り物から1点ものを作ったりしていました。
WWD:早かったですね。
神谷:当時は「サステナビリティはメーンストリームでないからそこに新しい価値、先進性があるのではないか」と思い、取り組んでいました。リ・スタイル プラスらしいカウンターカルチャーという意識です。
WWD:“やらねば”ではなく、“新しいことをしよう”から入っているところがいいですね。
神谷:ファストファッションが急成長する中、大量生産に対するアンチテーゼであり、「価格より価値が大事だ」という感覚が強かったですね。ファッションに機能性だけでなく情緒性や社会性を加味し、新しい価値観として提供したかった。
WWD:2020年にリ・スタイルをリモデルしたときには「パワー・オブ・チョイス、私たちができること」といった切り口でした。
神谷:この時はサステナビリティという言葉を使いました。ただしサステナビリティを絶対的なものではなく、多様性のひとつ “美しい選択”としてとらえたメッセージです。
小売り・ファッションとサステナビリティを結びビジネスとして成立させる難しさ
WWD:そういった変化に敏感なのは、バイヤーとしてさまざまなクリエイションや社会を見続けてきたからこそでしょう。
神谷:そうですね。年に4回ほど海外出張をするなかでブランドから「これは再生ポリエステルで作った」「これは残反だから少量しかない」といった話を多く聞くようになったり、プライズに選ばれるデザイナーもマリーン・セル(Marine Serre)をはじめ、サステナビリティに通じる考えがある人が増えたりするのを見聞きするなかで「そういう文脈になっているのだな」と受け取りました。ただ、それをお客さまに押し付けるのも違う。1人1人を否定せずに自分なりのスタイルを発信したかった。
WWD:特に、2022年3月に実施した「デニム de ミライ」は大きな話題になりました。
神谷:自分の中でもそういうマインドが醸成していたときに、たまたまヤマサワプレスを訪れて廃棄寸前の「リーバイス(LEVI’S)」のジーンズ“501”の山を見て「なるほど、やろう」と思えた。“デニムdeミライ”での活動は、本業であるファッションコンテンツとしての魅力を高めようとしたことや、様々な人を巻き込んで規模を大きくして発信性を高めたこと、つまり本業として当たり前のことに精一杯の力を入れて活動したことで、良い結果につながりました。
WWD:それがその後の、2023年「リスタイルアーカイブ」、デニム以外の生地の残反も加えた「ピース de ミライ」へとつながりました。 一連の取り組みの中で難しいと感じたことは?
神谷:本業である小売り・ファッションとサステナビリティを組みつけてビジネスとして成立させることです。サステナビリティの活動は「今すぐ儲からないとやらない」という訳でもない。本業の戦略とサステナビリティを組みつけることで、結果として“経済的価値”と“社会的価値”の双方の向上につながります。企画の質の向上と規模の拡大を通じて、経済性と社会性の双方を追求することは難しかったです。
また、衣食住で質の高い・幅広いコンテンツとの協業や小売り他社との連携もポイントになりました。社内外の多くの人を巻き込み最終的には一人のバイヤーの企画から、会社規模の企画に引き上げたことは誇りです。
顧客のサステナビリティに対する関心度の変化
WWD:顧客のサステナビリティに対する関心度の変化をどうみていますか?
神谷:2013年から行っている顧客アンケートをホームページでも公開していますが、「当社のサステナビリティ活動を知っていますか?」の質問に対してかつては20%程度だった「イエス」が23年には50%を超えました。また「三越伊勢丹が取り組むべき課題」に関しては、21年度までは「商品の品質」がトップだったのに対して、22年度からは「食品廃棄物の削減」となり、サステナビリティにつながることに関心を持たれていることがうかがえます。
自由回答には「百貨店だからこそ、ラグジュアリーとサステナビリティを両立させてほしい」という声や「百貨店をきっかけに知ることが増えた」もあがっています。印象的なのは一時期聞かれた「サステナビリティはトレンドだよね」という言葉が最近はほとんど聞かれなくなったことです。
ファッションとサステナビリティは両立する
WWD:神谷さんが考える「ラグジュアリー」とは?
神谷:まず、ラグジュアリーは高級や豪華という意味ではないということを最初にお伝えしたいです。目新しさだけでもない。自分と仲間の未来を豊かにしてゆくもの、と考えています。豊かになる、をほかの言葉に置き換えると、感動する、笑顔になる、成長する、新しいつながりができるといったこと。それを実感できるのがラグジュアリーだと思います。
WWD:「ファッションの伊勢丹」は最先端のファッションを扱っています。その中でファッションとサステナビリティは両立すると思いますか?
神谷:両立すると思います。社会価値も含めて考えること自体がクリエイティブだと思うから。
WWD:今後の課題は?
神谷:バイヤーは幅広いスコープを持ち情報収集していますがリソースとなる要素が個人や規模の小さい事業者になることも多い。いわゆる「人と人」の関係性からキッカケが生まれ、そこに寄り添った活動となることも多いため、企画やプロジェクトが属人化しやすく、企画の規模化や発展性、継続性を目指した仕組み化が難しくなってしまうことが課題です。
「デニム de ミライ」のときは、ヤマサワプレスでオープンファクトリーを開催し、社内メンバーに実際に体験し共感いただいたことで多くの人を巻き込むことができました。共感を生みだすためのストーリーを作り、メンバーを集め、経験を共にして、組織化と仕組み化をしていくというプロセスが非常に大切だと思いました。
